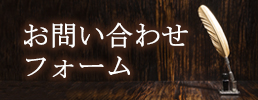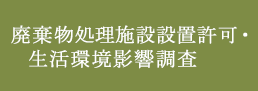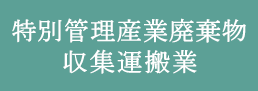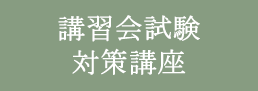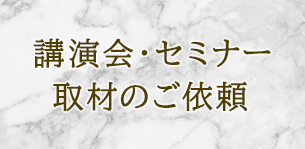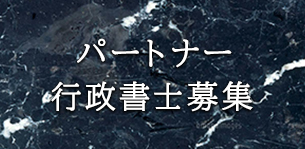私が行政書士として実務の中で廃棄物処理法(以後「廃掃法」と省略する)を読んできて十数年になります。
この法律の難しさは、よく知っているつもりです。
廃掃法は技術を法律で規制した法であり、技術の理解がそこに不可欠なこと、
その技術の定義自体が化学に依拠しており、化学的な理解を不可欠としていることがその難解さの要因ではないかと私は考えています。
たとえば、廃掃法2条には「廃酸」「廃アルカリ」という言葉が登場し、
この廃酸や廃アルカリには法令による定義は与えられていません。
そうすると、この廃酸、廃アルカリとはなにかを考えるにあたって、化学の一般的定義に依拠せざるをえないわけです。
高校レベルの化学でさえ、酸やアルカリの定義は「アレニウスの定義」と「ブレンステッド・ローリーの定義」という複数の定義が与えられており、
どうもリトマス紙のような単純な話ではないわけです。
ところが実務上は、そのような判断はなされていないわけです。
まずは、液状の産業廃棄物を廃酸または廃アルカリとして扱い、
そのpHを確認したうえで、廃酸または廃アルカリと分類して排出することになります。
もっとも、排出段階で排出事業者は通常それが酸性かアルカリ性かは知っているでしょうから、その認識のとおりに取り扱っているとも言えます。
pHが2.0以下ですと、これは著しい腐食性を有する廃酸として特別管理産業廃棄物に位置づけられます。
また同様に、pH12.5以上の廃アルカリも特別管理産業廃棄物です。
すると、pH2.0を超えるもの、またはpH12.5未満の液状の産業廃棄物は、廃酸または廃アルカリと位置づけられることになるのです。
これではただ単に、液状の廃棄物から腐食性廃酸と腐食性廃アルカリを控除したものを廃酸・廃アルカリと定義しているようにも思えます。
ところで、酸性でもない、アルカリ性でもない、中性の液体であればこれは産業廃棄物には該当しないのでしょうか。
今回の記事に後述していますが、法令の規定上、廃掃法施行令2条の産業廃棄物の品目毎の定義に当てはまらない廃棄物は、産業廃棄物には当たりません。
廃酸でも廃アルカリでもない中性の液状廃棄物は産業廃棄物に当たらないように見えます。
ところが、化学的には厳密な中性はないわけです。
全ての液体は、それが水道水であろうがペットボトルの名水であろうが、pHは僅かにでも7.0から傾くわけで、それに合わせて廃酸または廃アルカリに分類する必要があります。
ここで廃酸、廃アルカリの定義は廃掃法にはなく、化学に依拠しているのです。
しかし、化学的に厳密という理由で水道水やペットボトルの水が廃酸であったり廃アルカリであったりするのは、一般には大いに違和感があることでしょう。
液体の産業廃棄物は、排出事業場でミックスされて排出されることがあります。
この場合、pHが7.0付近でときに酸性、ときにアルカリ性を示す可能性があります。
この場合は、都度pH測定が難しければ、酸性とアルカリ性の混合物として扱うべきかと思います。
この法規定の仕方は産業廃棄物の判断手順とは異なっています。
技術と化学を法律で規定するということは、法律の定義を化学に委任することでもあります。
法律を読んでいくと最後は、廃酸・廃アルカリとは何か、或いは焼却とは何かのような「難問」に当たってしまいます。
言葉の定義は法令内で自己完結しません。
もちろん、行政側が解釈の指針を通知や要綱で提示してくれていることがありますので、その際は原則としてそれを利用します。
ただし、法治主義国家の大原則である「法律による行政の原理」は行政権を法律で縛ることにその本旨があるはずです。
行政は法律の解釈権を独占しているわけではありません。
ときに化学の知見を基にした法解釈を行政権に説明していくことも事業者としては必要になると私は考えています。
廃掃法の難しさは、化学に定義を依拠していること以外にもあります。
廃掃法は歴史的に、汚物掃除法、清掃法という法律の前身を持っており、明治以来の歴史があります。
時代が違えば、廃棄物の内容も異なり経済社会における価値も変わります。
当然、法律が保護すべき法益も変化します。
また、昭和45年の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の制定後も、廃掃法は法改正を繰り返しており、その都度「増改築」を繰り返してきたわけです。
増改築を繰り返した法令の宿命なのですが、条文も非常に読みにくいものになっています。
そこには「生活環境の保全」だけでなく、清掃法時代からの「公衆衛生」という保護法益を今もなお残しています。
さらに現代の廃掃法には、排出の抑制や分別、再生等、3Rという価値観をも合わせ持っています。
時代とともに加えられた雑多な価値観の基に、増改築を繰り返した難解な法令こそが今の廃掃法ではないでしょうか。
私はここ数年、自ら学ぶことだけではなく、誰かに教えるために廃掃法の講義をしています。
廃棄物処理業務を専門にしたいと考える行政書士に対して廃掃法の講義をしたり、新入社員の社員教育として講義をしてそれをzoomで生公開したりしています。
他人に廃掃法を講義するにあたって、何度も読んできたはずの条文を読み、何度も同じ講義をしていますが、その都度ちょっとした気づきがあったりします。
また、社員に対して、私が作成した廃掃法の試験を月1回実施しては、事務所内の知識の確認もしています。
その中で気づいたことがあり、今回はそれについても少し触れておきます。
廃掃法と接していく中で、廃掃法もやはり法律であり、法解釈は他の法律の解釈と同様の手順を踏むべきであると実感させられています。
それは、廃掃法の解釈も法学の一部としてなされるべきであるということ。
廃掃法の用語の定義は確かに化学に依拠していますが、それだけでなく、廃掃法の解釈も確立した「法解釈のしきたり」に則ってなされるべきであるとも、改めて痛感するのです。
私の廃掃法講義の最初の方の説明で、必ず廃掃法2条を読みます。
廃掃法2条1項には、「廃棄物」の定義が書かれています。
「ごみ、粗大ごみ・・・(略)汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの」というのが「廃棄物」の定義です。
この廃棄物の列挙は、限定列挙ですか、それとも例示列挙ですか、ということを必ずお聞きするわけです。
その後、2条4項の「産業廃棄物」の定義も併せて読みます。
4項1号には「燃え殻、汚泥・・・(略)」と産業廃棄物が列挙されているわけですが、これらは限定列挙ですか、それとも例示列挙ですかと改めてお聞きします。
最後に廃掃法施行令2条の「紙くず」「木くず」等、1号から13号までの「政令で定める廃棄物」を読み上げまして、これらは例示列挙ですか、それとも限定列挙ですか、とお聞きしています。
廃掃法2条1項の「廃棄物」の列挙は例示列挙です。
あくまでも例示列挙ですので「廃棄物」のひとつである「廃プラスチック類」はここには列挙されていません。
次に廃掃法2条4項の「産業廃棄物」の列挙も例示列挙です。
「産業廃棄物」のひとつの「繊維くず」は含まれていません。
最後に廃掃法施行令2条の政令で定める廃棄物の列挙は、限定列挙です。
ですので、ここには全ての産業廃棄物が列挙され尽くされており、それ以外の産業廃棄物は絶対に存在しません。
漫然と条文を読んでいると、つい読み飛ばしてしまいそうなところですが、ここをはっきりとさせることが私の解説のねらいです。
廃掃法2条2項には「一般廃棄物」について、産業廃棄物以外の全ての廃棄物と定義されています。
「産業廃棄物」は一応明確に法定されており、「一般廃棄物」については廃棄物から産業廃棄物を控除することで余すところなく定義しています。
そうすると、最も重要になるのは実は「廃棄物」の定義になるわけです。
ところが、「廃棄物」の法律上の定義には、「汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの」という曖昧な概念を残していることになるのです。
そのなかでも特に曖昧ゆえに問題になりそうなものは「不要物」概念ではないかと思います。これらの問題点からおから事件が生まれ、総合判断説にたどり着いたのです。
以上のように条文解釈のための考え方は、法学の世界または裁判実務で培われた「法解釈のしきたり」に則っておこなうべきです。
廃掃法解釈のバックグラウンドには、少なくとも化学の知見と法解釈のしきたりが必要で、それらを欠くとせっかくの三段対照の条文集に当たってみても、妥当な結論を導くことができないという可能性があるのです。
(河野)