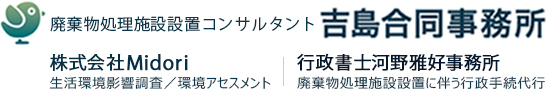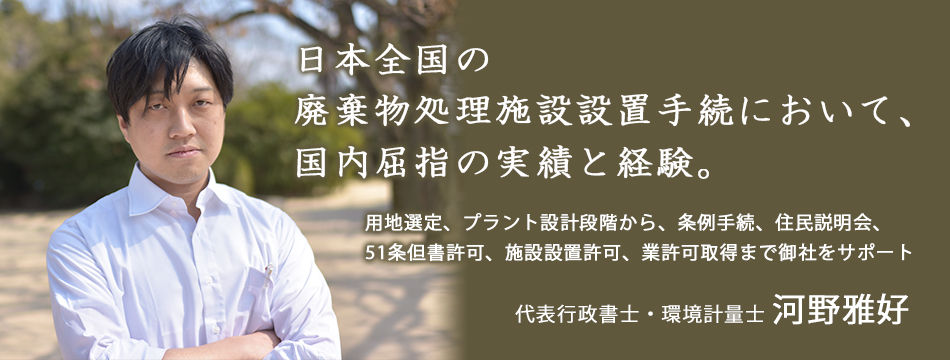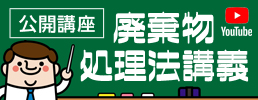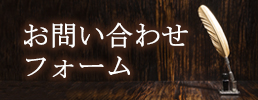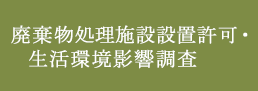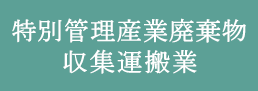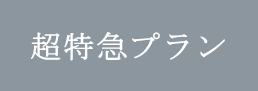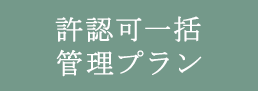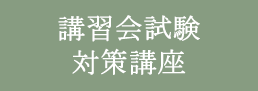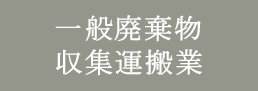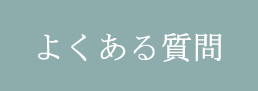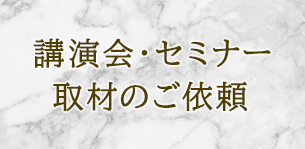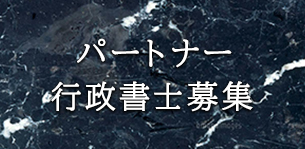産廃業許可申請書に添付する事業計画書について
産業廃棄物収集運搬業の許可申請書に添付する事業計画書は、
まさしく許可申請の要となる重要な書類です。
今回は、事業計画について解説してみます。
| この記事の目次 |
収集運搬の事業計画とは廃棄物をどう処理するかの計画
産業廃棄物収集運搬業許可申請書という書類の中に、事業計画書があります。
事業計画というと、企業が銀行融資を受ける際に提出するみたいなものをイメージしてしまいそうですが、
産廃の許可申請に添付する事業計画は、全く異なります。
産業廃棄物収集運搬業許可申請の事業計画とは、
- どこで発生したのか?
- どのような産業廃棄物か?
- その排出量は?
- どうやって処分するのか?
を記載した計画書のことです。
廃棄物処理の流れは逆有償
収集運搬業というのは、原則として、
排出場所で積み込んだ産廃を処分場に持っていくことを商売とすることです。
また、言い方を換えれば、排出者から料金を受け取り、運搬した後に処分業者に料金を支払う商売でもあります。
通常の商売は、商品の流れ(売主→買主)とお金の流れ(買主→売主)が逆方向です。
商品をもらわないとお金払わないよ、お金もらわないと商品渡さないよ、と言える関係なのです。
ところが、廃棄物処理業の特徴は、
ゴミの流れ(排出者→処理業者)とお金の流れ(排出者→処理業者)が同じなのです。
この廃棄物処理に関する特徴のことを、逆有償と呼びます。
このことが、不法投棄(野焼き、埋める)等の温床になるために、
廃棄物処理業を法律で規制し、行政が監督しているのです。
どんな廃棄物がどこからどのくらい排出され、
どこに運搬されてどのように処分されるのかを詳細に記載するのが、
許可申請書につける事業計画でした。
事業計画について少し解説してみます。
事業計画はまず産業廃棄物を品目ごとに記載する
まず、「どのような廃棄物か?」を特定するために、品目という概念を使います。
廃プラスチック類とか、汚泥とか、金属くずとか、いろいろあります。
産業廃棄物処理業の許可は、この品目に応じて出ます。
産廃の運搬の許可を持っているからといっても、何でも運搬できるわけではありません。
品目を指定されて許可が出るので、許可が出た品目のみしか運べないのです。
1枚の許可証には複数の品目を乗せることが可能ですので、
新規で許可を取得する際にはできるだけ多くの品目の許可を取得する方が一般的には望ましいです。
のちのち、品目を追加するとなると変更許可という別の許可申請が必要になってきます。
事業計画の運搬量は実現可能な数値を
事業計画には、運搬する廃棄物の運搬量を記載しなければなりません。
これは、現場から排出される量と、収集運搬業者の運搬施設の能力、
そして処分場の処理能力を勘案して計画しなければなりません。
ガソリンスタンドから廃タイヤ(廃プラスチック類)5千本が排出されることは、まず考えられません。
軽トラ1台で月に100トンの木くずを運搬するというのも、無理があります。
また、処分場にはたとえば破砕機があり、その破砕機には処理能力があります。
処理能力を超えた運搬量を計画すること自体、無計画な計画と言えるでしょう。
運搬量は、様々な要素を勘案しながら適当な量を算定します。
産業廃棄物の搬入先はどこか
次に、その廃棄物をどこに持っていくか。
例外もありますが、一般的には次の3つが多いと思います。
- 中間処理場
- 最終処分場
- 積替保管施設
一番多いのは、中間処理場へ持ち込むケースです。
ここで中間処理され、一部はリサイクルへ、残りは最終処分等へ回されます。
事業計画に記載する運搬先のほとんどが、この中間処理場です。
中間処理には様々な処理方法があります。
破砕、圧縮、焼却、選別、脱水などなど。
中には、産廃の性状からして不適切な処理方法もあります。
たとえば、がれき類を破砕することはありますが、
石綿含有産業廃棄物であるがれき類を破砕するというのは、当然認められません。
他にも、汚泥の焼却施設というものはありますが、
建設現場から排出された汚泥を焼却施設に持ち込むことはありません。
排出場所と処理方法の整合性がとれていなければ、事業計画として不適切ということです。
他にも、リサイクル可能な産廃をいきなり最終処分場に持っていくことは、
あまりにも経済的でなく、計画としても不適切でしょう。
適切かつ実現可能な事業計画を
事業計画というのは、実際に運搬するであろう計画と、
近い将来運搬する可能性が高い計画を記載することになるかと思います。
その際に、実現性の高い計画を描いておかなければ、申請先は適切な事業計画とみなしてくれません。
下手な計画を出してしまうと、許可される品目が減ってしまうことがありえます。
そうならないように、上記の点に留意して計画を立てていただければと思います。
もちろん行政書士は、事業計画策定もお手伝いします。
(河野)