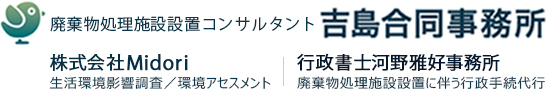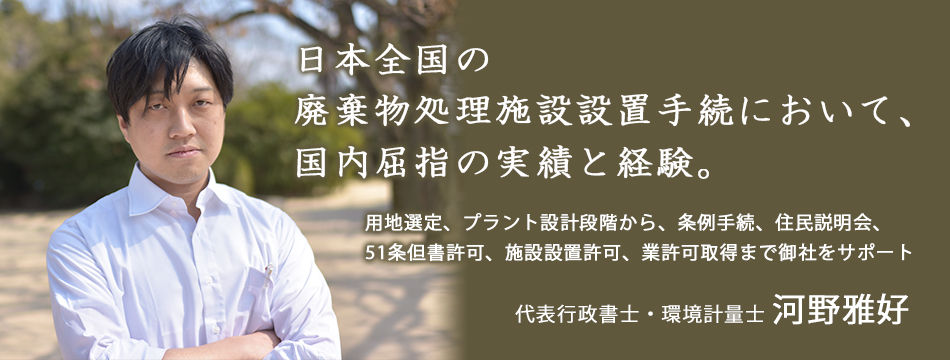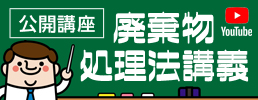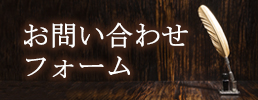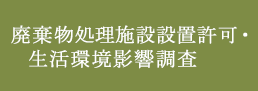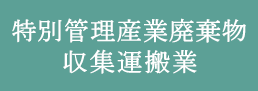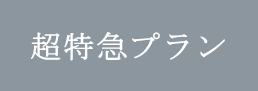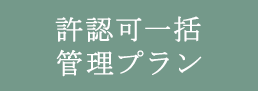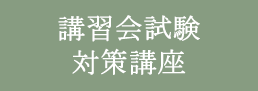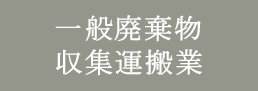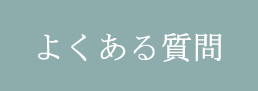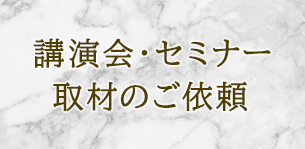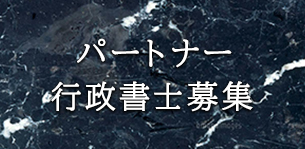原則、(特別管理)産業廃棄物収集運搬業では、排出元事業者から中間処理施設ないし最終処分場までの間、(特別管理)産業廃棄物を直送することとなっております。
これを、『産業廃棄物収集運搬業(積替保管を除く)許可』と称します。
産業廃棄物の収集運搬は、原則直送と定められています。
例外として、以下の3つのケース等においては、産業廃棄物収集運搬業の積替保管を含む許可申請を行って許可を取得することにより、下記のような事業を行うことが可能になります。
- 離島から産廃を運搬する際、船舶を用いて運搬。積み下ろし先の港に係留し、車両に載せ替える行為が積替保管行為だとみなされた場合、積替保管を含む許可を取得していなければ事業を行うことが出来ない。
- 運搬する混合廃棄物の中から、手選別で有価性の認められるもの(金属等)を取り出して売却したい。手選別を行うため、積替保管を含む許可を取得。 手選別後、有価性の認められない廃棄物のみ処理施設まで運搬する。
- 廃家電を排出場所で引き取る際、小型車両に積載し、一旦事業所の積替保管場所に持ち帰って積み下ろし、運搬先を同じくするまとまった量の廃家電といっしょに大型車両に積み替えて、処理施設まで運搬する。 輸送コスト削減のため、積替保管を含む許可を取得。
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の「積替保管を含む」とは、排出元事業者で(特別管理)産業廃棄物を収集したのち、自社の積替保管施設に一旦持ち帰り、保管したあとで、中間処理施設ないし最終処分場まで運搬することを指します。
「積替保管を除く」申請の場合、許可申請を行ってから許可証が発行されるまでの期間は平均で2ヶ月程度ですが、 「積替保管を含む」の申請の場合、準備期間を含めて平均半年~1年がかりとなることがほとんどです。
役所での事前相談にて、「産廃の排出場所」「産廃の品目名」「産廃の保管場所」「保管場所は建屋内か屋外か」「保管方法(容器を用いた保管等)」「保管量」「保管施設にてどのような作業が必要になるか」等々話し合います。
事前相談の内容を踏まえ、事前協議書の作成・提出を行います。
事前協議書が受理され、補正のプロセスを経て役所の立ち会い検査が行われます。 事前協議書にて申告した通りの積替保管場所レイアウトであることを確認されます。 数々のチェックポイントをクリアした時点で本申請へと進みます。
本申請が受理されたのち、書類の補正を行います。 スムーズに進んだ場合、許可申請日から起算して平均2~3ヶ月程度で許可決定となります。
許可決定後、許可番号が発行されますので、積替保管場所に掲げる看板(許可表示)を作成・掲示します。掲示後、実際に事業を開始することが可能になります。
上記フローが一般的な「積替保管を含む」許可取得までの流れとなりますが、審査の厳しい自治体の場合、積替保管施設の近隣の住民への説明会(住民説明会)が必要とされたり、更に厳しい自治体では、ごく稀に生活環境アセスまで求められることもあります。
ご相談・お見積りご希望の際には、
- 「積替保管を含まない」収集運搬業の許可をお持ちかどうか
- 「積替保管を含まない」品目名、「積替保管を含む」品目
- 積替保管を行う目的
- (分かれば)積替保管施設の予定地の用途地域や地目など
- 屋外保管か、建屋内保管か等、どのようにして保管を行う計画でいらっしゃるか
お電話でお問い合わせいただいても構いませんし、もし口頭でお伝えいただくことがご面倒であれば、ページ下部の専用のお問い合わせフォームのリンクからお問い合わせいただくことも可能ですので、是非ご利用下さい。
「積替保管施設を含まない」収集運搬業の許可申請とは異なり、お問い合わせ時点でのお見積りは出来かねます。予めご了承下さい。
個々のケースによって料金が異なります。また、申請先自治体によって申請の難易度も異なるため、まずはお客様から聞き取りをさせていただき、自治体への調査等を経た後でお見積りへと進ませて下さい。
積替保管関連記事
カッター廃液の適正処理と積替保管
続きを読む
遅々として進まない処分業・積替保管の手続について
続きを読む
積替保管、処分場の土地入手のリスク
続きを読む
積替保管や処分業許可の費用算定の悩み
続きを読む
「できれば欲しい積替保管」について
続きを読む
積換保管の難しさ・・・
続きを読む
積替保管施設の設置と許可の管轄
続きを読む