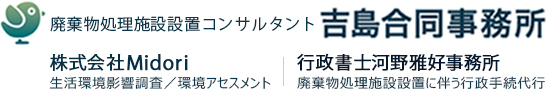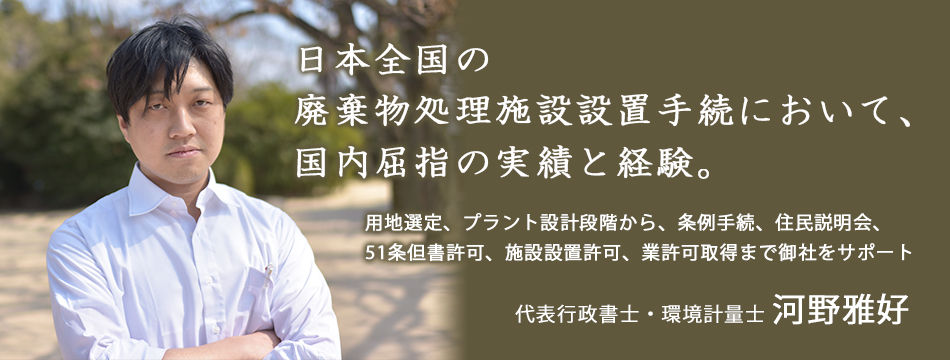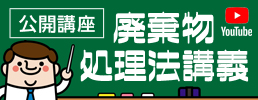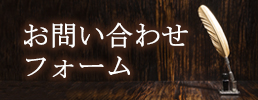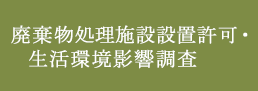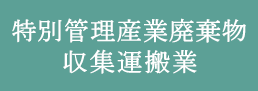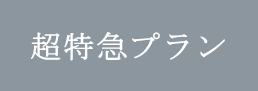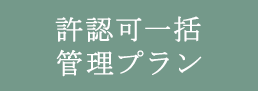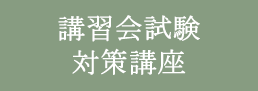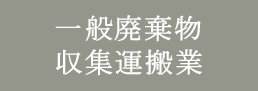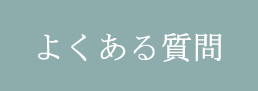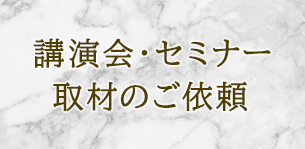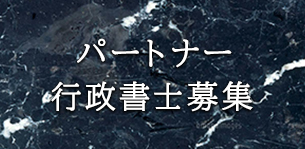産廃業者をリスクに晒す危険な許可管理
当事務所では、年間に300件以上の産業廃棄物収集運搬業許可申請を代行しています。
これだけの件数を取り扱う行政書士事務所は、日本中探してもおそらくほぼないと思います。
日本全国47都道府県に産廃業の許可を有する企業では、
きっと許可申請手続を内製していると思います。
というのも、日本中の産廃業許可申請手続のノウハウを持っている外注先の確保は難しく、
社内部署でやるよりないというのが実情ではないかと感じています。
私は、月間申請件数が50件を超えることもあります。
誰よりも多く産廃業許可申請をしてきたからこそ、語れることがあります。
数多くの許可申請を内製している企業の許認可手続の御担当者に、
ぜひ読んでいただきたいことがあり、今日の記事を埼玉県の浦和のタリーズより執筆いたします。
| この記事の目次 |
許可の管理を担当者1名に任せてはいけない
『許認可管理の鉄則』
許可申請書の作成とその管理を、1人の人に任せてはいけない
企業内でありがちな話。
「許認可手続の担当者は、◯◯さん』
この場合、彼または彼女は、会社の持つ全ての許可の管理をしながら、
時期に合わせて申請書や変更届の作成をすることになります。
管理をしながら、作成をする。
作成をしながら管理をする。
このような状態というのは非常に危険で、
いつ事故が起こるかわからないという危うさを組織にはらんでいる
ということになります。
許可管理失敗の行先は手続き忘れによる許可失効
許認可管理における一番の危険性はすなわち、手続忘れによって許可が飛んでしまうこと。
取り返しのつかない損失を生み、下手すると会社の経営危機を招くことも。
前にも記事に書きましたが、許可の管理はものすごく責任重大なのに、
企業にとっては生産性の低い事務作業。
許可の管理をしながら許可申請書の作成をするという状態。
これは、手続事務をセルフチェックしてるだけのようにも思えますが、
もっと本質的に、危ないんです。
許可申請の書類作成と管理を同時にできる人はいない
当事務所では、年間に300以上の申請書類を作成し続けているわけです。
申請書類を作成する、という業務に当たるときに、
その手続を管理するという視点は、完全に抜け落ちます。
申請書類の作成は、例えるなら計算ドリルを解いているような仕事時間。
一方、許可の管理は夏休みの旅行計画を立てるような時間の使い方。
計算ドリルを解きながら旅行の計画を立てられる方がいますか?
許可管理件数が多くなると、
申請書類作成時間が容赦なく仕事時間に幅を効かせてきます。
そして、その合間に許可管理計画を立てなければならない。
書類作成は納期が見えやすいので、疎かになるのは必ず許可の管理の方です。
私は誰よりも許可の管理をしてきたので、よくわかります。
それがExcelシート1枚で片付くような生易しいものではないということを。
安全な許可管理には、計画化と分業が必須
例えば当事務所では、
①短期的な申請予定と②許可の作成と③中長期的な許可の管理に対して、
3つに分業をしています。
①申請書類作成部門のリーダーが申請予定計画立案
②申請書類の各作成担当者は作成に集中
③長期的な管理は、データベースを元に申請書類作成に携わらない職員が担当
許認可の管理には、分業は必須です。
作成をしながら管理ができる人はまずいません。
分業こそが、事故を防ぐ唯一の方法です。
社長が許認可管理に無関心なまま、
「◯◯さん、許認可の管理と作成全部お願いね」
というのが、問題です。
担当者にお願いねというのは、
①許可申請書の作成
②許認可の管理
のいずれかでなければなりません。
①の場合、社長が許認可の管理に徹して、作成を担当者に任せるべきでしょう。
一方、②の場合は、実際に書類作成に当たるのは、
◯◯さんの部下(内製)か、行政書士(外注)か、ということになります。
外注の行政書士に任せたとしても、それは申請書作成までが一般的で、
許可の管理ごと任せるというケースは稀でしょう。
何度も繰り返すように、許可申請書の作成と管理は同時にしてはならないからです。
行政書士事務所と許可管理
当事務所では、許可申請書作成に加えて、この許認可管理までも外注できる事務所を目指してきました。
そのために、当事務所でも作成と管理を3つに分業することで、
事故が起きないようなシステムを作っているのです。
当事務所に御依頼いただくときでも、きっと企業のご担当者は、
独自の許認可管理をしていると思われます。
それくらい、許認可は企業経営にとって重要なものです。
当事務所では、企業独自の管理は、許認可管理において、
ダブルチェックのもう1つ上の、トリプルチェックを意味しています。
(河野)